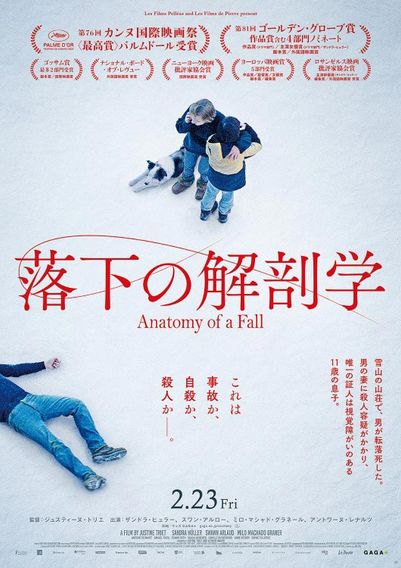前回の映画評から少し時間が空いてしまいましたが、また映画評を書こうと思います。
今回扱う作品は2023年11月3日公開「ゴジラ -1.0」です。ALWAYSシリーズや「永遠のゼロ」などを手掛けた山崎貴監督が脚本・VFX・監督を務め、浜辺美波・神木隆之介が出演しています。終戦直後を舞台にした本作では、焼け野原から復興を遂げようとする東京が無残にもゴジラによって襲われます。戦時中特攻隊に選ばれながら出撃をためらい終戦を迎えた敷島浩一やその仲間たちがゴジラの駆除に向かい、絶望的な戦況の中で彼らは唯一の希望にすべてを託す・・・というあらすじになっています。
2016年の「シン・ゴジラ」以来7年ぶりの実写ゴジラ映画であり、またゴジラ70周年ということで公開前後にはかなり宣伝もいれて、各種メディアでも盛り上がっています。さらに実際に見たという人によるSNSでの反響もかなり大きく、名実ともに現在最も注目を集めている映画だと思います。
自分が映画をみているなかで感じた最初のインパクトはゴジラの質感でした。ゴジラの背びれにあたるサンゴのような突起からはゴツゴツとした感触が手に取るように伝わりました。またゴジラが立ったときの、生物としては不格好な腹の出方で、とてもスタイルが良いとはいえない胴体を、縦横無尽に動かす姿には生き生きしたはつらつさを感じました。その不格好な四肢をもったゴジラが復興途上の東京を破壊しつくさまは、パニックの場面でもありつつ同時にゴジラファンとして「もっとやれ!」的な爽快感さえ感じさせるものがありました。これはやはり現代CG技術の旗手である山崎監督のなせる業なのでしょう。この点はゴジラという題材をフルに活用しつつ、観客の度肝を抜く迫力を出した点で評価されるべきポイントであると考えます。
CGや特撮などの技術面は他の多くの人が語るでしょうから自分はこの程度にしておきます。それよりも自分が語りたいのは、2016年の庵野秀明監督による「シン・ゴジラ」との差異です。なぜシン・ゴジラと本作の違いを語りたいかというと、それは明らかに本作は「シン・ゴジラ」がやらなかったことを描いて、ほとんど対立軸として位置づけられる作品であるからです。両作品とも由緒ある国産ゴジラ作品として「お約束」的な側面は踏襲しつつも明らかに方向性の異なる映画となっています。
シン・ゴジラの主人公は日米政府の政治家や高級官僚などのエリートであり、彼らの政治的な駆け引きやいびつながらも一つの目標に進むチームワークを中心に物語が進みます。そんなシン・ゴジラではパワーエリートではない人間はほとんど出てきません。一方本作の主人公敷島は言ってしまえば敗残兵であり、玉砕した(ということにされている)戦地から復員してきた負け組です。彼の周りにいる人々も何らかの形で戦のダメージを負った人間たちです。政府の役人や軍関係者はまったくといっていいほど出てきません。戦災以上の国家の危機なのに進駐軍を含めた軍事・政治の関係者が不自然なほどに出てこないのは、やはりシン・ゴジラとの対比を打ち出したかったのだろうと思います。
そしてシン・ゴジラではエリートたちが練り上げた計画を実行するために官民が総力をあげてゴジラの駆除に乗り出します。そして主人公グループはその作戦実行にたいして指示監督する立場のまま物語が終わります。しかし本作では主人公やその身の回りにいる人間が陣頭にたち、そして実際に生身の人間が容赦なくゴジラから攻撃をくらい死んでいきます。あくまで主人公たちは体制側の人間として作戦・用兵に徹する、トップダウン型の作品であるシン・ゴジラと、民間主導で主人公たちは身の危険を顧みずにゴジラに挑むボトムアップ型の本作、というふうにもいえるかもしれません。
市民の側から見たゴジラ作品であるので、本作では当然彼ら市民の生活も描写し、彼らのかかえる葛藤、人間関係、恐怖も描きこんだものになっています。そしてそれはシン・ゴジラでは省略され、そのことによってシン・ゴジラが評価される点でもあります。ではここまでシン・ゴジラとの対立軸を打ち出し、シン・ゴジラで描かなかった要素を描いてきた本作は、その描きこみをゴジラ作品というフレームに落とし込めているでしょうか。
自分は、評価できる点もあるが、ゴジラ作品としてはミスマッチだった点もあるのではないかと思っています。前述したようにCGを駆使したゴジラの躍動感によって、市民の暮らしが破壊されることの容赦のなさは特筆すべき点があります。ここまで冷徹に破壊を描きこんだのはやはり評価すべきポイントです。明確に人がゴジラに殺傷されるシーンを作ったのも、徹底したリアリティのある表現として素晴らしいと思います。
しかし、主人公周辺の葛藤とその解消には納得できない点があります。本作で描かれている大きな構図としては、圧倒的な力で破壊しつくす怪獣にたいして、犠牲的な死をもって解決するのか、それとも生きて抗うのかーーまさに本作キャッチコピー「生きて、抗え。」のとおりーーというものになっています。主人公敷島は戦争で死ねなかった自分に対する情けなさと、自分のせいで死んでいった戦友たちの記憶にさいなまれながら戦後を生きている人間です。その敷島がとる選択はどのようなものであるかが本作の一大テーマになっています。問題はこの対立はちゃんと成立しているか、そしてこの作品では主人公が主体的に生を選びとっているようには見えないという点です。
すこし話はそれますが、ゴジラがどのような存在なのかをちょっと考えてみます。ゴジラはこれまでいろいろな語られ方をしましたが、その中でも有名なのがゴジラ怨霊説(英霊説)というものです。要はゴジラは戦争や戦災(とくに原爆)で無念のうちに死んでいった戦没者による集合的な霊のようなものなのだ、という話です。だからこそゴジラは、戦後のうのうと暮らしている日本とくに東京に襲来して恨みを込めた攻撃を行うし、自分たちの味わった苦しみ(放射線による攻撃)を与えるし、兵器などを忌み嫌う性質を持っている、というのがゴジラ怨霊説の解釈です。ゴジラ1作目公開は1954年で終戦から10年もたたないうちに公開されています。戦争というものがアクチュアリティをもっていった時期の表現として、ゴジラはギリギリのラインを攻めた作品だったのだろうとも考えられます。そして本作は、このゴジラ怨霊説を明確にとった作品だったと感じました。シン・ゴジラが災害的で無差別的な攻撃を仕掛けてきたのに対して、今回のゴジラは明確に人間に対して殺意をもって攻撃を行います。そして戦艦や飛行機をみると怨念のこもった攻撃をあたえます。つまり単なる災害的な存在ではなく、本作のゴジラは明確に意思をもって破壊行動を実行するように描かれています。なぜゴジラは復興途上の東京を襲うのでしょうか。本作の答えは、「戦没者の怨霊のメタファーだから」ということになるでしょう。
そのようにゴジラという存在を解釈してみると、本作の構図も理解しやすくなると思います。つまり怨霊であるゴジラはすべてを破壊し、生きとし生けるものすべてを死にいざなう存在です。戦中に自分のした行為によって戦死者を生んでしまったと考える主人公は、いったんはゴジラ側、つまりは自らの死によってそのトラウマや後悔に対処しようとします。しかし彼はその選択をとらず生きることを選択することになります。これが本作が描きたかったテーマの概略になります。
話は戻ります。確かに市井の人々の目線からのゴジラ作品ということで、彼らの葛藤を丁寧に描いている本作ですが、その「生きて、抗え」という主題が、怨霊であるゴジラに対して十分な対立として成立しているのかが本作最大の疑問点になってきます。つまり、確固たる意志で初代ゴジラの精神を継承して、これだけ素晴らしいCG技術を利用してかなり明確に怨霊としてのゴジラを描いているにも関わらず、その対立点ーー我々はゴジラにたいしてどう生きるべきなのかということに対する本作の答えーーが弱すぎるのです。確かに主人公が生を選び取るという過程は描かれています。終戦直後、打ちひしがれていた彼に、仕事仲間ができ、生活を共にするものができ、子供の成長を見ることができた。それによって彼は死による解決ではなく、生による解決という選択をしたのだと、映画では雄弁に語ります。ですが、彼が生を選ぶにいたったきっかけをよく見ると、すべて外発的なものでしかないのです、映画で描かれてきた関連する出来事はすべて偶然と主人公に対する甘やかしでしかありません。主人公自身が主体的に「生きる」ことを選び取った形跡がなく、すべて惰性のままゴジラと対面しているとも言えます。そのような貧弱な意志しか持たないものが、なぜ強固な意志をもつゴジラを打ち破れるのか、まったく納得できないまま映画が終わってしまいました。なにも考えなしに生きる人間たちがゴジラを海に沈めるシーンで、自分は恐怖すら覚えました。つまり主人公たちは生を選び取っているというだけで、無制限に称賛されるべきで、それに対立するゴジラは力づくにでも沈めるというのか、と・・・。主人公が生を選ぶという描写に説得力を持たせられていれば、あるいはいっそのこと生と死という対立軸を取っ払って別機軸で描ければ、もしかしたら本作はさらに良作になっていたのではないでしょうか。
ながながと批判的な内容を述べてきましたが、確かに映像としてのクオリティは群を抜いてよい作品です。そして大きなスクリーンと上質なサウンドによって、怪獣映画としての臨場感を十分に味わえる作品になっていますので、ぜひ映画館で見るべき作品だと思います。総合的には非常にオススメです!